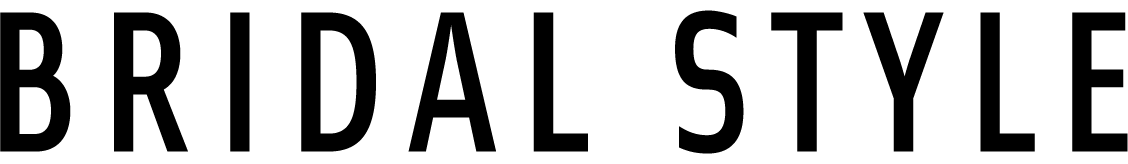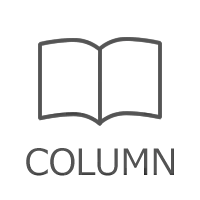【和装の選び方】和装の種類・文様からヘアスタイルまで!結婚式の和装選びガイド

前回の記事「【挙式の衣裳】ドレスと和装の魅力とデメリット〜スタイル別おすすめガイド」では、新郎新婦の婚礼衣装の特徴や魅力についてお伝えしました。
今回の記事では、「和装」に焦点をあててみていきましょう。
結婚式の衣裳といえばウエディングドレスのイメージが強いですが、最近では和婚ブームの影響もあり和装を着たいという人が増えています。
しかし、日本の伝統的な衣裳である和装を着て結婚式を挙げることに憧れているものの、
「和装にはどんな種類があるの?」
「どうやって選べばいい?」
「ヘアスタイルはどうしよう?」
など悩んでいる人もいますよね。
そこでこの記事では、和装の種類や選び方のポイントをご紹介します。和装のヘアスタイルについてもお伝えしているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
新婦が着る和装の種類

まずは、新婦が結婚式で着る和装の種類についてみていきましょう。新婦の和装は主に3種類に分けられます。ここでは代表的な和装3種類と、個性を出したい人にぴったりな新和装と十二単を加えた5種類の和装をご紹介します。それぞれに特徴や格式の違いがありますので、自分の結婚式のスタイルや希望するイメージに合わせて選ぶことが大切です。
白無垢
婦が着る和の婚礼衣装の中で最も格式が高いのが白無垢です。白無垢は日本の伝統的な花嫁衣裳で、挙式で着用することが多くなっています。掛下やその上から羽織る打掛、綿帽子、角隠し、草履などの小物も全て白で統一されているのが特徴。全て白色なのであまり違いがないように感じられますが、白無垢にもしっかりと柄があり生地の色も少しずつ違いがあります。
白無垢は「何色にも染まっていない純白の心」という意味が込められており、元々は「嫁ぎ先の家の色に染まる」という意味合いがありました。現代では花嫁の清らかさや新しい門出を祝福する象徴として愛されています。生地は正絹(絹100%)が一般的ですが、ポリエステルなど比較的リーズナブルな素材の白無垢も選択肢としてあります。
色打掛

色打掛は、鮮やかで華やかな色と柄が美しい婚礼衣装です。白無垢と同じく格式の高い衣裳で、白無垢以外の打掛は全て色打掛と呼ばれます。白無垢を挙式で着用した後、披露宴で色打掛を着るという人が多いですが、色打掛を神前式や和装の人前式で着用することも可能です。
色打掛の色には、それぞれ意味があります。例えば、赤は「情熱や愛情」、黒は「気品や凛とした美しさ」、青や緑は「若さや成長」などを表現します。柄も豪華で、金糸や銀糸を使った豪華な刺繍が施されていることが多く、花嫁を一層引き立てます。色選びは肌の色や季節感も考慮すると良いでしょう。夏場は涼しげな青や水色、冬場は温かみのある赤や金色など、季節に合わせた色を選ぶのもポイントです。
引き振袖
引き振袖とは通常の振袖とは違い、裾の丈を調節する「おはしょり」をせずに、長い裾を引きずって着用する振袖のことです。引き振袖は未婚女性の第一礼装で最も格式の高い衣裳となっています。引き振袖はお色直しで着ることが多く、色打掛とは違って羽織物がないため動きやすいのが特徴です。
引き振袖は色打掛よりもカジュアルな印象があり、若々しさを演出できます。特に歩くたびに裾が優雅に引かれる様子は、大変エレガントで写真映えも抜群です。色や柄は振袖らしく明るく華やかなものが多く、若い花嫁に人気があります。また、打掛に比べて着付けも比較的簡単で、動きやすいため披露宴での歓談やお色直し後のパーティーに適しています。
新和装
和婚の人気が高まるにつれて注目を浴びるようになったのが「新和装」です。新和装とは、和装の中に「洋」のテイストを取り入れた着物のこと。着物の素材にチュールやオーガンジーを使ったり、柄に蝶やバラなどを取り入れたりして「和」と「洋」をミックスさせて現代的なデザインになっています。素材自体が軽いため着物が重くなりにくいので、夏場に和装を着たい新婦におすすめです。
新和装は従来の和装にとらわれない自由なデザインが特徴で、伝統的な要素を残しつつもモダンで斬新なスタイルを楽しめます。例えば、着物の上にベールを合わせたり、西洋風の花柄や幾何学模様を取り入れたりと、和洋折衷の美しさを表現できます。パステルカラーや淡い色合いのものも多く、柔らかい印象を与えたい花嫁に向いています。また、レストランウェディングや少人数の披露パーティーなど、カジュアルな会場との相性も良いでしょう。
十二単

十二単とは平安貴族の衣裳で、一般人は着られないのでは?と思う人もいるかと思いますが皇族以外の人も着用できるため婚礼衣装として着ることができる衣裳です。お雛様が着ている衣裳というイメージが強い人も多いかもしれませんね。12枚の着物を着用するため重厚で高貴なイメージになり、他の和装とはひと味違った雰囲気を味わえます。十二単は着付けのために広い仕度部屋や介添人が必要になるので、十二単を着用できる会場は限られます。気になる人はしっかりと調べてみてくださいね。
新郎が着る和装の種類

新郎が結婚式で着る和装の種類は大きく2種類あります。
新婦の和装に合わせて、新郎も和装を選ぶことでより統一感のある和婚が実現できます。
黒五つ紋付き羽織袴
黒五つ紋付き羽織袴は、新郎の婚礼衣装の中で最も格式が高い衣裳です。黒色の羽織の背中、両袖の後ろ、両胸の5か所に家紋が入っています。挙式と披露宴どちらでも着用できる衣裳です。
この装いは武家社会で発展した礼装で、現代の結婚式でも最も格式高い和装として重んじられています。羽織の下には白や灰色の着物(長着)を着用し、袴は縞柄のものを合わせるのが一般的です。家紋は本来、自分の家の紋を入れますが、最近ではレンタル衣装の場合、一般的な家紋(例えば「丸に三つ柏」や「丸に橘」など)が既についているものを選ぶことが多いです。特に白無垢姿の新婦と合わせると、厳かで美しい日本の伝統的な婚礼の姿を表現できます。
色紋付羽織袴
色紋付羽織袴は、黒ではなくグレーや白、紺など色が付いていて紋が1つまたは3つになっている衣裳です。黒五つ紋付き羽織袴よりもカジュアルなスタイルになるため、お色直しの時に着用する人が多くなっています。
色紋付羽織袴は、格式はやや落ちるものの、より個性を出しやすい衣装です。特に白や灰色の羽織は、新婦の色打掛や引き振袖と合わせやすく、現代的でスタイリッシュな印象を与えます。紋の数が少ないことで、より普段着に近い雰囲気になり、ゲストとの距離感も縮まるでしょう。また、最近では和洋折衷のスタイルとして、羽織袴の下にカラーシャツを合わせたり、洋装の小物を取り入れたりするアレンジも人気です。二次会や披露宴の後半など、よりリラックスした雰囲気を演出したいときにおすすめです。
和装の選び方のポイントご紹介!

和装はあまり馴染みのない人も多いため、何を基準に和装を選べばよいのか迷ってしまいますよね。ここでは、和装を選ぶときにチェックして欲しいポイントを詳しくご紹介します。
準備は通常、結婚式の6カ月〜3カ月前から始めるのが理想的です。和装は洋装と違って体型補正が比較的容易なため、体型の変化に対応しやすいというメリットもあります。
こんな新婦になりたい!理想の雰囲気を考える
ドレス選びの時と同じく、まずはどんな雰囲気の新婦になりたいのかをイメージしてみましょう。
「日本の伝統的な雰囲気を大切にしたい」…白無垢
「大人っぽく凛とした雰囲気にしたい」…黒や赤など鮮やかな色打掛
「淡いカラーで和と洋どちらも取り入れたい」…新和装
など、なりたい雰囲気によって着物の色や柄が決まってきますよ。
理想の雰囲気を考える際には、結婚式の会場や季節も考慮に入れると良いでしょう。
例えば、神社での挙式なら白無垢が調和しますし、モダンな会場なら斬新なデザインの色打掛や新和装が映えます。また、春夏なら明るく爽やかな色合い、秋冬なら深みのある色合いを選ぶと季節感も表現できます。ピンや青などの淡い色は春、赤や橙などの華やかな色は夏、茶や黄金色などの渋い色は秋、黒や深緑などの落ち着いた色は冬、というように季節に合わせた色選びも和装の魅力を引き立てるポイントになります。
着物の柄や文様をチェック!

和装を選ぶときに第一印象を左右する色も大切ですが、実は着物の文様も重要なポイントのひとつ。新婦の婚礼衣装には、「吉祥文様」という縁起が良いとされる柄が描かれています。文様の意味を知っておくと、より一層着物選びが楽しくなりますね。代表的な吉祥文様をみていきましょう。
鶴

鶴は「長寿」の象徴とされている上、鶴は夫婦になった相手と一生添い遂げるという習性があることから「永遠の愛」という意味もある文様です。婚礼衣装では2羽で描かれることが多くなっています。
夫婦鶴は特に人気の高い文様で、一緒に飛ぶ姿や向かい合う姿など、様々な構図で描かれます。金糸や銀糸で刺繍されることも多く、華やかな印象を与えてくれます。鶴と亀が一緒に描かれている「鶴亀」の文様もあり、これは「長寿と繁栄」を象徴する縁起の良い組み合わせとされています。
松竹梅
真冬も耐えて緑を保ち続ける「松」、まっすぐに伸びる「竹」、寒さの中でもいち早く花を咲かせる「梅」の3つが描かれた文様。大変な状況の中でも耐えられる「忍耐力」や「長寿」「美しさ」の象徴とされています。
松竹梅は日本の伝統的な「歳寒三友(さいかんさんゆう)」として尊ばれ、厳しい環境にも負けない強さの象徴です。結婚生活においても困難を乗り越える力を示唆しており、特に神前式で好まれる文様です。松の青々とした葉、竹のしなやかさ、梅の優雅な花の組み合わせは、視覚的にも美しく、和装に格調高さをもたらします。
熨斗
熨斗は神様へのお供え物の「熨斗鮑」が元になっています。「長寿」や、古くから縁起物とされている熨斗を束ねることで「多くの人から祝福を受ける」などの意味があります。
熨斗文様は、細長い形が特徴的で、通常は水引のようにカラフルな色彩で表現されます。打掛全体に散りばめられることもあれば、裾や袖に控えめに配置されることもあります。紅白の組み合わせが特に祝い事に相応しいとされており、慶事の象徴として和装に華やかさをプラスします。最近では、熨斗と桜や牡丹などの花を組み合わせた複合的な文様も人気です。
檜扇(ひおうぎ)
檜扇とは、平安時代の姫君が持つ薄いヒノキの板で作られた扇のこと。末広がりな形で「繁栄」などの意味があり縁起が良いとされています。その文様は、広がる扇の形が「これから広がる幸せな未来」を象徴すると考えられています。打掛の裾や袖に大きく配置されることが多く、金糸での縁取りが施されることで格調高い印象を与えます。
檜扇と一緒に桜や菊などの花々が描かれることもあり、華やかさと上品さを兼ね備えた文様として人気があります。また、平安時代の雅な雰囲気を醸し出すことから、歴史や日本文化に興味のある花嫁に好まれる傾向があります。
花車
平安時代の貴族が乗っていた御所車に、華やかで美しい花が飾られた文様。神を招き寄せるとされており「たくさんの幸せが運ばれてきますように」という願いが込められています。その文様は、平安貴族の優雅な暮らしを彷彿とさせる豪華な意匠で、特に色打掛に多く見られます。車輪や屋根の部分が金糸で縁取られ、周囲に牡丹や菊などの花々が配されることが多いです。「幸せを運ぶ」という意味から、新生活への希望を表現するのにふさわしい文様とされています。
特に格式高い場所での結婚式や、歴史的な雰囲気のある会場での挙式に調和する文様といえるでしょう。
また、着物を選ぶときには文様の大きさにも着目すると◎。大胆に柄が描かれているものと全体的に細かく文様が描かれているものでは、同じ文様でもかなり着物の雰囲気が変わってきます。新婦の身長や体型によっても印象が変わってくるので、いろいろ試着してみるといいですね。
自分に似合う着物を選ぶ

自分が着たい色や柄の着物を選ぶのも大切ですが、着物によってはその人に合うものと合わないものがあります。せっかくなら、好みのデザインでなおかつ自分に似合う着物を選びたいですよね。ここでは、体格別の着物の選び方をご紹介します。
背が高い人
身長が高い人は、大きな柄もキレイに見せることができるため大柄の文様が似合うといわれています。かっこいい雰囲気にしたい人は、黒引き振袖もおすすめですよ。身長の高さを活かすなら、縦長のシルエットを強調する文様や、裾に向かって広がるデザインの着物が効果的です。
例えば、滝や流水のように縦に流れる文様、または高貴な印象の牡丹や菊の大柄などが映えるでしょう。また、色の面では濃い色や鮮やかな色も堂々と着こなせるため、赤や紫などの存在感のある色も良く似合います。背の高さを活かした凛とした佇まいは、特に神前式などの格式高い場での和装に映えることでしょう。
背が低い人
身長が低い人は、大きな柄だと身長の低さが際立ってしまうため細かな柄が似合うと言われています。縦に流れるような柄を選ぶとよりバランスが良くなりますよ。また、全体的に小さめの文様が分散しているデザインや、縦のラインを強調する柄が視覚的に身長を高く見せる効果があります。特に桜や梅などの小さな花模様、細かな幾何学模様などが良いでしょう。色選びも重要で、明るめの淡い色や、単色で統一されたデザインがスッキリとした印象を与えます。
裾の部分に控えめに柄が入ったデザインも、バランスが取りやすいです。小物使いでは、帯や髪飾りを少し高い位置に配置することで、全体のバランスを整えることができます。
体型が気になる人
体型が気になる人は、淡い色よりも濃い色の着物を選ぶと◎。濃い色の着物は全体を引き締めてくれます。なお、着物は妊娠中も着られる衣裳です。また、体型をカバーするなら、全体に散りばめられた小さな文様より、特定の部分に集中した大きめの文様の方が視線を集中させる効果があります。例えば、肩や袖、裾などに豪華な刺繍や金箔があしらわれた着物は、そちらに注目が集まります。
帯の位置や幅にも工夫ができます。少し高めに帯を締めることで、スタイルアップ効果が期待できますし、幅広の帯は腰周りをすっきり見せる効果があります。色彩的には、黒や紺、深緑などの濃色は全体を引き締めてくれますし、縦のラインが強調されたデザインも有効です。和装の魅力は、着付けの技術で体型をカバーできる点にもありますので、経験豊かな着付師に相談するのも良いでしょう。
和装におすすめのヘアスタイル
和和装の時に、どのようなヘアスタイルにするかによっても雰囲気が変わってきます。和装を引き立ててくれるおすすめのヘアスタイルをみていきましょう。ヘアスタイルは顔の形や髪質、そして何より着用する和装との調和が大切です。試着の際には、ヘアスタイルのイメージも合わせて確認するとより具体的なイメージをつかむことができます。

かつら
伝統的な雰囲気を大切にしたいのであれば、かつらを使用したヘアスタイルがおすすめ。「文金高島田(ぶんきんたかしまだ)」という格式が高く伝統的なスタイルが、結婚式で和装を着るときのかつらの代表的なヘアスタイルになっています。
文金高島田は、頭頂部から後頭部にかけて大きく盛り上がった形状が特徴的で、白無垢や格式高い色打掛との相性が抜群です。かつらを使用することで、自分の髪の長さや量に関係なく、完璧な日本髪のスタイルを実現できます。また、結い上げた髪の重さや疲労感を感じることもなく、長時間の挙式や披露宴でも安心です。最近では、従来のものより少し小ぶりで軽量化されたかつらも多く、より快適に着用できるようになっています。特に神前式や格式高い会場での挙式に臨む花嫁に人気のスタイルです。
日本髪
かつらをかぶるのは抵抗がある…という人におすすめなのが、地毛で結う日本髪。地毛で結うため自然な髪型になります。ある程度の長さやボリュームが必要になるため誰でもできるわけではないので注意が必要。地毛で日本髪にしたい時は、スタイリストさんとよく相談してくださいね。
地毛で作る日本髪には様々なスタイルがあります。代表的なものに「新日本髪」があり、これは伝統的な日本髪を現代風にアレンジしたもので、少し崩しつつも和の雰囲気を保った髪型です。髪の長さがミディアム以上あれば挑戦できることが多く、髪が短い場合は部分的にエクステンションを使うこともあります。地毛で結う利点は、かつらよりも軽く、自然な質感が出せることです。また、顔周りの髪を少し残して柔らかい印象にしたり、華やかな簪(かんざし)や花の髪飾りを用いたりすることで、個性を出すこともできます。白無垢よりも色打掛や引き振袖に合わせることが多く、カジュアルな和婚スタイルに調和します。
綿帽子
綿帽子とは、髪の上からかぶる白い袋状の布のこと。和のヘアスタイルの中で最も格式が高く、一般的には白無垢を着るときにかぶることができるとされています。先ほどご紹介した文金高島田と合わせることが多いですが、最近では洋髪や日本髪用の綿帽子もあるようです。その真っ白な姿が花嫁の清楚さを象徴し、特に神前式での挙式に相応しいとされています。
かぶり方にもいくつかのバリエーションがあり、顔周りの見え方や全体のシルエットに影響します。例えば、少し前に傾けてかぶると顔をより小さく見せる効果があり、反対に真っ直ぐかぶると厳かな印象になります。
綿帽子は挙式のときだけかぶり、その後の記念写真や披露宴では角隠しに変更することも多いです。綿帽子をかぶるときは、その下に綿が入った小さな枕(まげ)を置き、形を整えることが一般的です。この「まげ」の大きさや形によっても、全体の印象が変わりますので、試着の際にはさまざまなパターンを試してみるとよいでしょう。
角隠し
角隠しとは、かつらや日本髪を包むようにつける帯状の白い布のこと。綿帽子とは異なり、顔の輪郭や頭頂部が見えるため、かんざしが見えて華やかさがアップする被り物です。その名の通り女性の角(つの)を隠すという意味があり、嫁入り前の娘の気性の激しさを象徴する「角」を隠すという風習に由来しています。綿帽子よりもフォーマル度はやや下がりますが、髪飾りや簪が見えるため華やかさを演出できます。角隠しは白無垢だけでなく、色打掛との相性も良く、特に「綿帽子→角隠し」とお色直しをする花嫁も多いです。
角隠しには様々な付け方があり、顔の形に合わせて調整が可能です。額を広く見せたい場合は高めに、顔を小さく見せたい場合は低めに付けるなど、微調整することで最も美しいシルエットを作り出せます。また、角隠しと一緒に使う髪飾りも重要です。白無垢には白や銀の簪、色打掛には色とりどりの花簪など、衣装に合わせた髪飾りを選ぶことで、より統一感のあるスタイルが完成します。
洋髪
最近では和装に洋髪を取り入れる人も多くなっています。洋髪に和テイストの髪飾りを取り入れたり、あえてルーズなスタイルにしたりと人それぞれ。洋髪にする場合は、着物に負けないようにある程度ヘアスタイルにもボリュームを持たせるとバランスが良いですよ。
洋髪と和装の組み合わせは、伝統的すぎず、かといって現代的すぎない、絶妙なバランスを生み出します。アップスタイルは特に人気で、シニヨンやまとめ髪に和風の髪飾りをプラスすることが多いです。例えば、生花や造花の簪、かんざし、組紐の髪飾りなどを取り入れることで、和の要素を表現します。また、編み込みを取り入れたり、毛先をゆるくカールさせたりと、柔らかな印象を与えるスタイルも人気です。
和装を着用できる挙式スタイルはこれ!

最後に、和装を着用できる挙式スタイルについてみていきましょう。
和装が着られる挙式スタイルは4種類あります。それぞれの挙式スタイルによって、和装の選び方や組み合わせも変わってきますので、自分たちの希望する雰囲気に合わせて選ぶとよいでしょう。また、会場選びの際には、和装での挙式に対応しているかどうかも確認することをお忘れなく。
神前式
神前式とは、神社に祀られている神様の前で結婚を誓う日本の伝統的な挙式スタイルです。神社の神殿で行われることが多いですが、専門式場やホテルなどにある神殿でも神前式を挙げることができます。神前式については「【神前式の流れ】儀式の流れや衣装、費用の内訳をご紹介!」で詳しくご紹介しているので、参考にしてみてくださいね。
仏前式
仏前式とは、仏教教えに基づいて行われる挙式で、仏様やご先祖様に結婚の報告をする挙式スタイルです。お寺で行われることが多くなっています。仏前式については「【仏前式】メリット・デメリットから費用まで!神前式との違い・服装まで完全ガイド」で詳しくご紹介しています。
人前式
人前式とは、式に来てくれた親御さんや親族、友人などゲストに結婚の誓いを立てる挙式スタイルです。人前式は宗教要素がないので、和装で挙式することができます。最近では「和装人前式」が人気で、人前式の中に和の儀式を取り入れる人もいるようです。人前式について詳しく知りたい人は「【人前式の魅力】演出アイデア・費用・実例から準備スケジュールの完全ガイド」をチェックしてみてください。
茶婚式
茶婚式は、茶道の「一期一会」の精神を大切にした新しい和婚スタイルです。通常、茶室や和室で行われ、新郎新婦がお互いにお茶を点て、それを飲み合うことで結婚の誓いを表現します。静かで落ち着いた雰囲気の中、一つ一つの所作に意味を込めた丁寧な時間が流れるのが特徴です。茶婚式とは最近話題の和婚スタイルで、茶道の精神を取り入れています。茶婚式については「【茶婚式】和婚の新スタイル!挙式の流れや魅力、費用をご紹介」で詳しく紹介していますよ。
まとめ
この記事では、婚礼衣装の和装についてご紹介しましたがいかがでしたか。 和装といってもいくつかの種類があり、文様や色によって雰囲気が変わってきます。 ご紹介したように和装に合わせるヘアスタイルもいろいろな種類があるので、なりたいイメージに合わせて選んでみるといいでしょう。 この記事を参考に、おふたりにぴったりの和装を選んでくださいね。
和装は、伝統的な衣装に身を包むことで、日本の美しい文化や歴史を肌で感じることができます。結婚式当日はもちろん、前撮りやお色直しなど、複数の和装を楽しむカップルも増えています。試着の際には、衣装だけでなく、ヘアスタイルや小物も含めたトータルコーディネートをイメージしましょう。また、和装は着付けに時間がかかるため、当日のスケジュールにも余裕を持たせることが大切です。
和装は日本の伝統美を体現する衣装ですが、「伝統を守りながらも自分らしさを表現する」という新しい楽しみ方も生まれています。ぜひ自分たちの個性や二人の関係性を象徴するような和装選びを楽しんでください。美しい和装姿で迎える特別な一日が、一生の思い出となりますように。