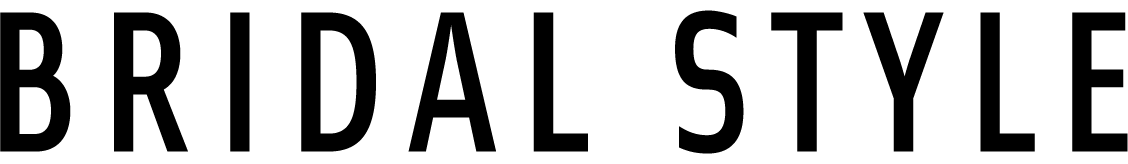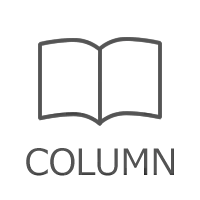【仏前式】メリット・デメリットから費用まで!神前式との違い・服装まで完全ガイド

仏前式(ぶつぜんしき)は神前式とともに、日本古来からある挙式スタイルの1つです。
新郎・新婦が仏壇や神棚の前に座り、今生かされていること、ふたりが出会ったこと、ふたりが生まれて変わっても結ばれることを仏さまと先祖の前で誓います。仏教の教えに基づいた結婚を神聖なものとして捉え、結婚の祝福を仏様に求める意味合いがあります。
一般的に寺院で執り行われ、新郎・新婦やその家族ゆかりのお寺が選ばれることが多いですが、自宅で執り行われるケースもあります。
仏前式とは?その意味と特徴
仏前式(ぶつぜんしき)は、仏教の教えに基づいた伝統ある日本の結婚式スタイルです。新郎・新婦が仏壇の前で永遠の愛を誓い、先祖への感謝と共に新しい人生の門出を祝福する厳かな儀式となっています。近年では、伝統的な価値観を大切にしながらも、カップルの希望に応じて現代的なアレンジを加えることも可能な柔軟な挙式スタイルとして注目を集めています。

仏前式の歴史的背景
仏前式の起源は、奈良時代にまで遡ります。当時、仏教が日本に伝来し、寺院での結婚の儀が行われるようになりました。特に江戸時代以降、庶民の間でも仏前での結婚式が一般的となり、地域社会や家族の絆を深める重要な儀式として定着していきました。明治時代に入ると、神前式が広まり始めましたが、仏教徒の間では依然として仏前式が好まれ、現代でも日本の伝統的な結婚式の形式として大切に受け継がれています。
仏前式の宗教的意義
仏前式には、深い宗教的な意味が込められています。仏教では、ご縁を結ぶことを大切にし、二人の結婚も数々のご縁が重なって実現したものと考えます。そのため、仏前式では以下のような要素が重視されます。
- 先祖への感謝の念
- 仏の教えに基づく夫婦の在り方
- 来世まで続く縁の誓い
- 家族や周囲の人々との絆の深化
仏前式を執り行う際のマナー

式場に到着する際は、静かに入場し、仏壇や神棚の前で深々とお辞儀をすることが重要です。
式の進行中は、スマートフォンの電源を切り、周囲の参列者の気持ちを乱すようなことは避けましょう。衣装は、新郎は羽織袴、新婦は白無垢や色打掛といった伝統的な和装を着用し、神聖な雰囲気を演出することが望ましいでしょう。また、数珠や白い扇子などの小物を持参し、宗教的な雰囲気を高めることも大切です。
式中の所作としては、正座などの所作を心がけ、両手を合わせて敬虔な態度で祈ることが求められます。供物の手渡しや線香の手渡しなど、宗教的な作法に沿った所作を丁寧に行うよう気をつけましょう。
式の最後には、両親や神仏に対して深く感謝の気持ちを込めて、お辞儀や拝礼を行うのがマナーとされています。新郎新婦が心を込めて祝福の意を表すことで、参列者全員で神聖な雰囲気を共有することができます。
このように仏前式は、式の意義を十分に理解し、敬虔な態度と適切な所作、そして伝統的な和装の着用が求められます。宗教的な側面を尊重し、参列者全員で厳粛な雰囲気を醸成することが大切です。
参列者のマナーと心得
参列者は、仏教の厳かな雰囲気を損なわないよう、以下のようなマナーを心がける必要があります。
- 式場入場時は、静かにゆっくりと着席する
- お経や法話の際は、姿勢を正して合掌する
- 写真撮影は、指定された時間以外は控える
- 私語や大きな物音を立てることは避ける
- お焼香の作法を事前に確認しておく
特に重要なのは、仏前での礼拝の仕方です。両手を胸の前で合わせ、静かに頭を下げることで、仏様への敬意を表します。また、お焼香の際は、三拝九拝の作法に従い、丁寧に行うことが求められます。
衣装と所作の基本
衣装は、新郎は羽織袴、新婦は白無垢や色打掛といった伝統的な和装を着用し、神聖な雰囲気を演出することが望ましいでしょう。また、数珠や白い扇子などの小物を持参し、宗教的な雰囲気を高めることも大切です。所作については、以下のポイントに注意が必要です。
- 正座の姿勢を保つ(身体的な理由がある場合は事前に相談)
- お辞儀は丁寧にゆっくりと行う
- 数珠の持ち方や扱い方に気を配る
- 三拝九拝の所作を確認しておく
- 焼香の作法を習得する
これらの所作は、事前に練習しておくことをお勧めします。特に、長時間の正座や複雑な作法が必要な場面もあるため、当日スムーズに行えるよう準備することが大切です。また、体調や身体的な理由で正座が難しい場合は、事前に寺院に相談し、対応を検討することができます。
仏前式の費用相場
仏前式の費用は、挙式場所や規模、演出の内容によって大きく異なります。一般的な寺院での挙式費用から、お布施、衣装代まで、予算に応じて柔軟な対応が可能です。全体の費用感としては、神前式よりも抑えめに設定できることが特徴です。

寺院での挙式費用の目安
寺院での挙式基本料金は、一般的に15万円から50万円程度が相場となっています。これには、以下のような費用が含まれます。
- 本堂使用料:5万円〜15万円
- 僧侶への御礼:3万円〜10万円
- 式次第の準備費用:2万円〜5万円
- 仏具使用料:3万円〜10万円
お布施の相場と意味
お布施は、寺院や僧侶への感謝の気持ちを表す大切な習わしです。一般的な相場は3万円から10万円程度で、地域や寺院によって異なります。お布施の種類には、以下のようなものがあります。
- 寺院へのお布施(本堂使用料を含む)
- 導師へのお布施
- 楽器奏者へのお布施(雅楽などを入れる場合)
このお布施は、単なる料金ではなく、仏教の教えを説き、儀式を執り行う寺院への感謝の印として捧げるものです。金額の多寡ではなく、感謝の気持ちを込めることが大切とされています。
予算を抑えるポイント
予算を抑えながらも、厳かで心に残る仏前式を挙げるためのポイントをご紹介します。
- 平日挙式の活用
- 参列者数の適切な調整
- シーズンオフの活用
- 近隣寺院の利用
- 衣装のレンタル活用
これらの工夫により、本来の仏前式の意義を損なうことなく、予算内での執り行いが可能となります。
仏前式の準備
仏前式を執り行う上で、式の意義や流れ、宗教的な作法について、事前に十分に理解しておくのが良いでしょう。神社や寺院の関係者、あるいは経験豊富なウエディングプランナーなどに相談し、必要な知識を得ておきましょう。
さらに、両家の宗教観や信仰心を確認し、参列者全員が納得できる形式で式を進めるよう配慮することも重要です。宗教的な背景の異なる家族の理解を得るため、事前の調整が不可欠です。
当日の進行についても、司会者や神職など、式の進行を担当する人物を選定し、役割分担を明確にしておきましょう。また、撮影やビデオ撮影など、記録の方法についても事前に決めておくと安心です。
装飾や演出についても、宗教的な雰囲気を損なわない範囲で検討する必要があります。生花や和装小物の使用など、伝統的な要素を取り入れることが望ましいでしょう。
このように、仏前式を円滑に執り行うためには、事前の十分な準備が不可欠です。カップルは宗教的な知識を深め、両家の理解を得ながら、厳粛な雰囲気を醸成できるよう心がける必要があります。
挙式までのスケジュール

仏前式の準備は、計画的に進めることが重要です。以下の順序で準備を進めていくことをお勧めします。
- 6ヶ月前:寺院の選定と日程確定
- 4ヶ月前:衣装の選定、参列者リストの作成
- 3ヶ月前:招待状の発送、仏具の確認
- 2ヶ月前:当日の進行確認、写真撮影の打ち合わせ
- 1ヶ月前:最終打ち合わせ、所作の練習
- 1週間前:最終確認、天候対策の検討
必要な持ち物リスト
当日に必要な持ち物は、宗派や寺院によって異なる場合がありますが、一般的には以下のものが必要となります。

- 仏前式の必需品
- 数珠(新郎新婦用)
- 扇子
- お布施
- 身分証明書
- 衣装関連
- 着付け用小物
- 着替え
- 履物
- その他
- タイムスケジュール表
- 参列者リスト
- 化粧直し用品
事前の打ち合わせポイント
寺院との打ち合わせでは、以下の点について確認が必要です。
- 式次第の詳細と所要時間
- 当日の集合時間と場所
- 写真撮影可能なタイミング
- 雨天時の対応
- お布施の金額と渡し方
- 参列者への注意事項
仏前式の服装
仏前式における服装は、伝統と格式を重んじた装いが基本となります。新郎新婦はもちろん、参列者も仏前式にふさわしい装いを心がけることが大切です。特に和装の場合は、着付けの予約や着崩れ対策など、事前の準備が重要になります。
新郎新婦の服装選び
新郎新婦の装いは、仏前式の雰囲気を決定づける重要な要素です。伝統的な和装が一般的ですが、最近では和洋折衷のスタイルを選ぶカップルも増えています。

白無垢と色打掛の違い
白無垢は、清らかさと神聖さを象徴する伝統的な花嫁衣装です。一方、色打掛は華やかさと格式を兼ね備えた装いとして人気があります。それぞれの特徴は以下の通りです。
- 白無垢の特徴
- 清純さと神聖さを表現
- 伝統的な仏前式に最適
- 儀式的な雰囲気を演出
- 色打掛の特徴
- 華やかで格調高い雰囲気
- 多様な柄や色合いから選択可能
- 写真映えが良い
羽織袴のマナー
新郎の羽織袴は、格式と威厳を感じさせる伝統的な装いです。着用時は以下の点に注意が必要です。
- 羽織と袴の色の組み合わせ
- 帯や小物の選び方
- 履物の種類と色
参列者の服装マナー
参列者の服装も、仏前式の厳かな雰囲気に配慮した選択が求められます。和装・洋装どちらを選ぶ場合も、以下のポイントを押さえることが大切です。
和装と洋装の選び方
- 和装の場合
- 訪問着や付け下げが基本
- 華やか過ぎない柄を選ぶ
- 帯や小物も控えめに
- 洋装の場合
- 膝下丈のワンピースやスーツ
- 派手な色は避ける
- 露出の多い服装は不適切
NGな服装
仏前式にふさわしくない服装として、以下のようなものが挙げられます。
- 黒の喪服
- 派手な色や柄の衣装
- 露出の多い服装
- カジュアルな装い
- 白基調の服装(花嫁への配慮)
仏前式と神前式の違い
仏前式と神前式は、日本の伝統的な結婚式の二大形式ですが、その背景となる宗教や儀式の内容に大きな違いがあります。それぞれの特徴を理解することで、より自分たちらしい挙式スタイルを選ぶことができます。

宗教的な違い
仏前式は仏教の教えに基づき、神前式は神道の教えに基づいています。この宗教的な背景の違いは、以下のような特徴となって現れます。
- 仏前式の特徴
- 先祖供養の要素が強い
- 来世までの縁を重視
- お経や焼香がある
- 神前式の特徴
- 神々への誓いを重視
- 現世での結びつきを祝福
- 神主による祝詞がある
式の形式の違い
儀式の進行や所作にも、それぞれの特徴が表れます。
- 仏前式の儀式
- お経と法話
- 焼香の儀
- 誓いの言葉
- 仏前での記念撮影
- 神前式の儀式
- 修祓(しゅばつ)
- 三三九度の儀
- 玉串奉奠(たまぐしほうてん)
- 神前での記念撮影
費用面での違い
一般的に、仏前式は神前式と比べて費用を抑えることができます。その理由として以下が挙げられます。
- 本堂使用料が比較的リーズナブル
- 装飾や演出が控えめ
- 必要な仏具が少ない
- お布施の相場が明確
仏前式 当日の流れ

仏前式の流れは、まず新郎・新婦が仏壇や神棚の前に座り、仏前に向かって三拍子で礼をするところから始まります。その後、仏前で仏様にお祈りをして、新郎・新婦が結婚の誓いを立てます。誓いの内容は、新郎・新婦それぞれが自由に決めることができますが、基本的には相手を愛し、尊重し、支え合うことを誓うものが多いです。
1. 会場の準備
まず、仏前式を行うために、会場に仏壇や神棚を設置します。仏壇には、仏様や祖先様の位牌やお香、お花などを飾ります。神棚には、神様や祖先様のお守りやお神酒、お菓子などを用意します。
2. 入堂
次に、参列者が会場に着席し、新郎・新婦が仏壇や神棚の前に座ります。通常、新郎は右側に座り、新婦は左側に座ります。
3. 敬白文朗読(けいびゃくもんろうどく)
司婚者が、仏前式の開式の挨拶を行います。
4. 勤行(ごんぎょう)
仏壇や神棚に向かって、司婚者がお経を読み上げます。読み上げるお経は、新郎・新婦やその家族が信仰する宗派によって異なります。
5. お祈り
お経の読み上げが終わったら、新郎・新婦が仏壇や神棚に向かってお祈りをします。お祈りの際には、お香をたいたり、手を合わせたりします。
6. 司婚の儀(しこんのぎ)
お祈りが終わったら、新郎・新婦が結婚の誓いの言葉を述べます。誓いの内容は、自由に決めることができますが、基本的には相手を愛し、尊重し、支え合うことを誓うものが多いです。
7. 指輪交換
誓いの言葉が終わったら、新郎・新婦が指輪を交換します。指輪交換は、日本の結婚式では珍しい演出の一つで、感動的な場面となります。
8. 焼香(しょうこう)
新郎新婦の順に焼香を行います。
9. 誓杯(せいはい)
神前式の三三九度にあたるものです。
10. 法話
司婚者がふたりの仏前式での結婚について、お祝いの言葉とともに仏教の教えについてお話してくれます。
12. 退堂
すべての儀式を終え、新郎・新婦、両親、親族、来賓の順に退堂します。
個々の儀式や流れについては地域や宗派によって異なる場合があります。
仏前式のメリットとデメリット

メリット
- 日本の伝統的な結婚式の一つであるため、格式が高く、神聖な儀式として捉えられています。
- 仏教の教えに基づいた結婚式であるため、相手を尊重し、支え合うことが重要視されます。
- 六輝に基づく吉日を気にする必要がなく、いつでも式をあげられます。
- 他の挙式スタイルと比べて、比較的コストが抑えて挙式をあげることができます。
仏前式は、日本の伝統的な結婚式の形式を大切にできるメリットがあります。宗教的な意味合いが強く、神聖な雰囲気を演出できるため、カップルの信仰心や家族の宗教観を反映した心の通った式を行えます。仏壇や仏具を使うことで、先祖への感謝の気持ちを表現することができ、日本文化を尊重した式となります。宗教的な背景を持つ家族や親族にも喜ばれ、式に参列する人々の心に深く残る一日となるでしょう。このように、伝統的な日本の結婚式の様式を大切にしつつ、神聖な雰囲気と先祖への敬意を表現できるのが、仏前式の大きな魅力といえます。
デメリット
- 宗派が違うと自分たちが望む寺院で執り行えない場合があります。
- 宗教色が強いため、宗教観の異なる家族や親族には抵抗感がある可能性があります。
- 信仰する宗派の違いによって意見がまとまらないあケースもあります。
- 神前式や人前式に比べ、式の進行が長くなる場合があります。
- 宗教的な制約から、式の演出や進行に柔軟性が少ない。
- 宗教的な知識がなければ、式の意味合いを十分に理解できない可能性があります。
仏前式にはいくつかのデメリットも存在します。まず、宗教色が強いため、宗教観の異なる家族や親族には抵抗感がある可能性があります。仏壇や仏具の準備、宗教的な作法の理解など、式の準備が煩雑になりがちです。また、式場の選択肢が限られ、費用が高くなりやすい傾向にあります。宗教的な制約から、式の演出や進行に柔軟性が少なく、宗教的な知識がなければ、式の意味合いを十分に理解できない可能性もあります。このように、宗教的な側面が強いことが、仏前式の実施にあたっての課題となります。カップルの信仰心や家族の理解を得ることが重要であり、事前の十分な準備が必要不可欠といえるでしょう。
仏前式Q&A
結婚式を控えたカップルからよく寄せられる疑問や不安について、具体的にお答えします。特に初めて仏前式に参列する方にとって、知っておきたい情報をまとめました。

よくある質問と回答
宗派が違う場合はどうする?
宗派が異なる場合でも、以下のような対応が可能です。
- 新郎新婦どちらかの寺院で執り行う
- 両家の了解を得て中立的な寺院を選ぶ
- 宗派を超えた仏前式を提案する寺院を探す
大切なのは、両家の理解を得ながら、お二人の希望に沿った形を見つけることです。
お布施の渡し方は?
お布施の渡し方には一定の作法があります。
- 新品の白封筒を使用
- 中包みには熨斗を付けない
- 当日は受付で預かってもらう
- 直接手渡しする場合は両手で丁寧に
親族以外の参列は可能?
基本的に参列者の制限はありませんが、以下の点に配慮が必要です。
- 寺院の収容人数の確認
- 参列者への事前マナー説明
- 写真撮影のルール周知
- 席次の配慮
これらの質問は、事前に寺院に確認することで、スムーズな準備が可能となります。不明な点があれば、遠慮なく相談することをお勧めします。
まとめ
縁やつながりに感謝し、来世の繋がりも誓う仏前式は、日本の伝統的な結婚式の形式として、深い意味と価値を持っています。近年では、伝統を守りながらも、カップルの希望に合わせた柔軟なアレンジも可能となっており、より親しみやすい挙式スタイルとして選ばれています。
式の準備から当日の進行まで、さまざまな配慮が必要となりますが、両家の理解と協力のもと、心に残る素敵な一日を創り上げることができるでしょう。大切なのは、お二人らしさを大切にしながら、参列者全員で祝福し合える温かな雰囲気を作ることです。
見た目だけではなく、日本の伝統を重んじ、縁に感謝し、未来までも誓う仏前式って素敵ですよね。